

手話と聾教育/手話を学んでみて思うこと
《最終更新日: 2024年11月28日》
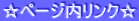
初めに: 私と手話の出会いとページ作成の意図
多くの人に手話を学んで欲しい理由
手話を学ぶにあたり「問題」と感じる事
手話表現を文字で説明すると…
…クイズ/ 英語と日本語
手話奉仕員養成講座と手話通訳者養成講座について
…手話を使えることと手話通訳は全く別なのに…?
状況別に必要な手話の能力
手話と英語の共通点
…日本手話ができると英語もできるようになる⁉
手話言語条例について
地域の手話出前授業の様子
↑2024年8月、手話サークルで行った小学校の出前授業で思ったこと。
最後に…
障がい者福祉・聾教育の歩み(年表)
英語を話すことにつながる英作文/ 余談・手話と英語
全日本ろうあ連盟
こちらのページは執筆途中です。自分の手話学習が進む中で、気持ちも変わっていく可能性があり、それに合わせて掲載記事も変わっていくと思います。ご了承いただいた上で、お読みいただけると幸いです。
初めに:私と手話の出会いとページ作成の意図
《最終更新日:2024年1月4日》
私は、2022年5月から、本格的に手話を習い始めました。手話について、また聴覚障碍者について、初めて知ったことも多く、驚きの連続でした。手話表現には、とても豊かな文化を感じるので、多くの人に関心を持っていただきたいと思っています。手話について興味がある方と情報を共有できればと思い、当サイトに手話関連のページを作ることにしました。
私が最初に手話と出会ったのは、以前、青少年相談員をしていた時です。地域の手話サークルの方にお願いし、小学3年生~6年生の子供達50人くらいに、手話の歌を教えてもらったり、小学生と聴覚障害者が交流するイベントを実施しました。これは、市内各地区の青少年相談員が集結し、それぞれの地区の活動を劇場で発表するという企画の一貫だったのですが、子供達は一生懸命取り組んでくれました。聴覚障害のある人達と交流するのは、私も含めて初めてだったので、最初は戸惑いもありましたが、皆さんがとても優しく接してくださったので、「子供達はきっと、障害者の方々に偏見を持たない大人になってくれるだろ~」と、期待が持てました。
発表会では、低学年は童謡の「さんぽ」、高学年は私がファンだったSMAPの「らいおんハート」(特権の乱用?
ただ、残念だったのは、「もっと手話を覚えたい」という子供達の要望に、答えてあげられなかったことです。私が手話をできれば良かったのですが、本を買って勉強しようとしましたがむずかしくてよくわからず、当時はスマホも無かったので、「こう言いたい時はどうやるの?」と聞かれても、教えてあげられませんでした。また、青少年相談員の活動も「手話」に限ったものではなかったので、聴覚障害のある人達の交流も一過性のものとなってしまいました。聴覚障害のある人との交流の機会がないと、手話を学ぶ意識も遠のいてしまうと実感しました。
そんな私ですが、数年前、再び手話との出会いがありました。それは、私が所属しているテニスサークルに、聾の女性が参加してくれるようになったことがきっかけです。彼女は生まれつきの聾者ですが、とてもアクティブで、テニスもうまく、さらに発声は少しできるので、初めの頃メンバーは、少しは聞こえているのではないかと誤解してしまうほどでした。私は少しだけ手話の経験があったので、彼女に少しづつ必要な単語の手話を教えてもらい、簡単な会話ができるようになりました。通じる言葉が増えてくると、手話での会話が楽しくなります。昔、英会話やスペイン語会話を勉強し始めたころ、実際に外国人と話せて、ドキドキワクワクしたことを思い出しました。
そんな中、2022年5月から、市主催の手話奉仕員養成講座があるという事を彼女に聞き、一念発起して参加することを決めました。
講座に参加して、手話表現には、長く受け継がれてきた歴史や文化に関する表現も多く、その上、パントマイムや表情の表現も加わり、「とても豊かな文化なのだな~」と思うようになりました。ただ、手話が言語として正式に認められたのは、日本では2011年(平成23年)8月5日、「改正障がい者基本法」が公布された時と知りました。それまで、手話が言語として認められず、学校教育の中でも禁止された辛い時期もあったとのこと。手話が言語と認められるまで、関係者の方々は大変な苦労をされてきたことがわかりました。
私は2021年の夏、東京オリンピックのフェンシング会場でボランティアをやったのですが、その時のオンライン研修では、ほとんどの研修に手話通訳がついていました。手話を使えるというのは、ボランティアとしても素敵なことと感じていたので、聾者が手話を使うことを禁じられていた時代があったと講座で知り、大変驚きました。
今回、英語学習のホームぺージ内に「手話」の項目を入れたのは、多くの人に手話を知り、使えるようになって欲しいと思ったからです。聴覚障害者とのコミュニケーションを円滑にするのはもちろん、高齢化が進み、耳の遠くなる人も増えるであろう日本で、手話はコミュニケーションツールとして、大いに役立つと思いました。手や指を細かく動かすこと、聾者の文化に裏付けされた味のある手話を覚えるのは楽しいですし、指文字など、指を細かく動かすことは認知症の予防にもなると、認知症予防の講習で知りました。(2023年11月)
ただ、後にも書きますが、手話には日本手話と日本語対応手話があり、文法も違います。さらに手話表現には方言が多く、どの手話を覚えて良いか正解もわからず、最初は大変戸惑いました。動画やイラストなど、Web上で無料で学べる教材も増えているのですが、いざ自分で伝えたいことを手話にしようとすると、なかなか大変です。
手話も英語と同じで、せっかく覚えても使わなければ忘れてしまいます。頻繁に聴覚障害者の方と接する機会がないばあい、やはり独学できる環境も必要と思います。
そこで、これも
2025年11月15日~26日には、「ろう者のためのオリンピック」であるデフリンピックの100周年の記念すべき大会が東京で開催されます。(参考:
もっと気軽に、容易に手話を学習できる世の中になって欲しいと思います。手話ができる人が増えることで、聴覚障碍者と健常者の壁がなくなり、最終的には手話通訳が入らなくても、皆気軽に会話ができるようになれば良いのにな~と思います。
多くの人に手話を学んで欲しい理由
①少しでも手話ができる人が増えれば、優しい世界になる⁉
テレビなどを見ていると、「聾者はかわいそうな人」というようなイメージを持つことがありますが、実際、色々な聾者と触れ合ってみて感じたのは、「聾者も普通の人で色々なことをエンジョイして生きている」という事です。さらに、聞こえない分、「観察眼に優れている」と思える人が多く、交流していて刺激をもらえます。
今は、スマホなどでも簡単に会話は成り立ちますが、もし知らない言語を話す外国人の中に1人だけ入ったら、やはりとても不安になると思います。そんな時、一言でも自分のわかる言葉で話しかけてくれる人がいたら、嬉しいのではないでしょうか。
聾者の友人も、「ある店に行ったら、手話でありがとうと言われた」と、とても喜んでいたことがありました。手話を少しでも使える人が増えたら、良いな~と思います。
また、聞こえない人に、聞こえる音や音楽について話したら、不快な思いをさせてしまうかと思った時もありましたが、実際そんなことにはなりませんでした。聞こえない人に、どんな感じで聞こえるか説明すると、わからないことが理解できるので良いようです。
例えば、ウグイスがどんな感じで鳴いているか。「春の初めはテンポが変だったけど、段々上手になってきて、今はホーホケキョと、きれいに鳴いているよ」と説明したら、驚いていました。聞こえない人にとって、聞こえる人から情報を得る事は有意義のようです。因みに、その時の私は、ほとんど手話が出来なかったので、指文字とジェスチャーで伝えたのですが、何とか伝わり、楽しく会話できた気になりました。こんな程度でも、良いのではないでしょうか。
②小学校で手話を学ぶことは意義がある⁉
SDGsが叫ばれる中、聴覚障碍者の歴史や生活について学ぶことは、とても意味があることと思います。道徳の時間などに、毎年1時限でも、皆が学べるようにすれば、聴覚障碍者への理解が深まるだけでなく、他者の目線に立つことの大切さを学べ、共感力の向上にもつながると思います。(参考:
手話をテレビなどの媒体で目にすることが増えてきた現在、「手話を学びたい」と思う子供も増えているようです。ただ、残念ながら、一般的な生活の中で、聴覚障害者と出会う機会はかなり少ないと思います。是非、柔らかい感性を持つ小学生に、手話サークルなどを通して、聴覚障害者と実際に会い、触れ合う機会を作っていただきたいと思います。
因みに、
③高齢者の認知症予防にも手話は役立つ⁉
日本も高齢化社会になり、難聴の人も増えていると聞きます。そんな時、手話はとても役立つと思います。また、私の所属する手話サークルで、自治体主催の認知症についての講義を受けた際、講師の方からも「指を動かす指文字は、認知症の予防にもとても良いと思います。」と言われました。鏡の前で、指を動かしながら指文字の練習をしたり、手話を使った歌を練習するなども、脳の活性化に役立ちそうです。
個人的な話で恐縮ですが、私は手話の指文字を習っている際、利き手の右手の親指と人差し指の腱を負傷したことがあります。利き手で指文字を作るのが困難になり、一時、左手で練習しました。鏡文字のようになりましたが、利き手が回復するに連れ、今度は両手で指文字を作る練習をしてみると、これが指のリハビリにとても役立つことがわかりました。
「手話は言語」とやっと認められ、関係団体の方々の中には「手話は遊びの道具ではない」と思われる方もいると思います。しかし、多くの人が知らなければ、「言語は使えない物」となってしまう気がします。老化防止にも役立つと感じる手話。高齢者施設なども含め、多くの人に学んで欲しいと感じました。
手話を学ぶにあたり「問題」と感じる事
《最終更新日: 2023年12月8日》
手話が言語として正式に認められたのは、日本では2011年(平成23年)8月5日、改正障がい者基本法が公布された時とのことです。それまで、教育の中で手話を使うことが禁止された時期もあったようで、関係団体および関係者の方々は、大変な苦労をされてきたと聞き及んでいます。ただ、IT環境などが整い、情報収集環境が以前とは全く違うものとなった現在、手話の学習方法など、現状に合ったものに変えていく必要があるのではないかとも感じています
①聴覚障害者と接する機会が少ない。
手話を学んでいると、手話通訳者や手話講師の方から、「手話を学ぶには、実際に多くの聾者と交流するのが一番」と言われます。しかし、現実の生活の中で、聾者の方に会う機会は殆どありません。街角や電車内で、「手話を使っている人を見たことがある」という人はいても、「聾者の知り合いがいる」人は少ないと思います。私も、長い間そうでした。
さらに、手話に興味を持っても、学び方がわからない人も多いのではないでしょうか。手話サークルは各地域にありますが、実際参加するとなると、「場所が遠い」「活日や時間が合わない」など、気持があっても仕事や学校の都合などで、サークルに入会するのを諦めている人もいると思います。
聾者と聴者の生活圏が違い、聾者と接する機会が少ないことで、聾者の事を理解する機会がないことに、大きな問題を感じます。もっと気軽に、聾者と聴者が交流できる世の中になって欲しいと思います。
②手話を自習することがむずかしい。
英語もそうですが、言語を習得しようとする時、実際にネイティブ(その言語を母語とする人)と話すことが一番と言われることが多いです。ただ、英語も手話も一般的にはネイティブに毎日会って話すのはむずかしく、しっかり自習をできる教材がないと、言語習得はむずかしいと思います。
以前は、聴覚障害者が周りにいない場合、本などで自力で学習しなければなりませんでしたが、IT環境が整った今は、スマホやユーチューブなどの無料動画などでも手話を学べ、だいぶ良い環境になってきたと感じます。ただ、「自分が話したい内容を手話で表したい」となると、本の教材、ユーチューブ等の動画、ネット等で、実際に色々調べましたが、見つけることがかなりむずかしいことがわかりました。(2023年12月現在)
昨今、チャットGPTの活用も始まっています。無料で使えるような、優れた手話教材や翻訳ソフトを作ることは、それほどむずかしいことではないと思いますが、現在、満足行くようなものが見当たりません。これは、後で触れる、「標準手話が定まっていない」ことも原因かとも感じます。
このような状況下、「教材がないなら作ってみよう」と、2023年5月、地域の初心者向け手話奉仕員養成講座の後期が始まったことを機に、本気で手話のページをまとめ始めました。ただ、手話表現を文字で説明するのは、かなり無理があると私自身も理解しています。それでも、ないよりはマシと思って作ってること、ご理解いただければと思います
手話表現を文字で説明すると…
ここでちょっと、文章の説明だけで、正確な手話を再現できるか、実験したいと思います。次の説明に従い、自分で手話をやってみてください。
「左手の平を下に向けて胸の前に置き、左手の下を、人差し指だけ立てた右手の人差し指が、相手に向かうようにくぐらす。」
うまくできましたか。
これは「なぜ、理由、意味」を表す手話です
言葉だけで指の動かし方を説明するのは大変です。
With the start of the second half of a sign-language training course for beginners in the community in May 2023, I decided to make the pages to learn the sigh language in earnest. But it's really hard to explain the sign language in words.
I want to experiment to see if I can reproduce accurate sign language using only text descriptions.
Follow the instructions below to try sign language yourself.
"Place your left hand face down in front of your chest and raise your right index finger.
Run (or move) your right index finger with its tip facing the front, under your left hand horizontally.
Did you do well?
This is the sign language for "Why, Reason, Meaning."
It's very difficutlt to explain how to move fingers just with words, isn't it?
③日本手話と日本語対応手話があることが知られていない
手話を習い始め、「日本語対応手話」と「日本手話」というものがあるとわかりました。生まれつきの聾者は日本語と文法も異なる「日本手話」を使いますが、中途聴覚障害者や難聴の人には「日本手話」はむずかしいということもわかってきました。
難聴の人の中には、手話を全く理解できない人もいます。この辺に、問題を感じます。
中途失聴や難聴者の場合、話すことはできるので、語しながら日本語の語順に従って表現できる日本語対応手話を使うそうです。
日本語対応手話の場合、日本語を話しながら使いやすいので、補聴器や人口内耳で相手の声を聞き取る時の助けになるというメリットがあるとのことです。
中途失聴の場合、「手話がなかなか覚えらず、習得を諦めてしまう」という問題もあるようです。これは、手話を習う機会がなかった難聴の方にも当てはまることですが…。手話は聴覚障碍者にとって、とても優れた言語であると思うので、とても残念です。やはり、日本手話と日本語対応手話の違いを併記した、誰でも簡単に理解できるような文法書があればと思いました。実際、あるのかどうか、不明ですが…。
参考:
④手話表現に地域差(方言?)が多く、覚えにくい。
手話は、日本国内においても、地域ごとに発展してきたものなので、方言が多いことにも気付きました。そこに、文化があり、それぞれの地域の聾者が誇りを持って使っていることも学びました。しかし今は、インターネットで日本中がつながっています。以前のように、「地域内だけで通じる」ではなく、「全国的に通じる」手話が必要になってきていると思います。
「標準手話」というものがあるようですが、実際に手話を習って感じたのは、講師の先生方は、「手話は地域によって様々なので、間違いということはないので、全部の表現を覚えてください」と指導しています。結局、「これが標準手話」というのはよくわからず、色々な表現を教わることで、覚えることがむずかしくなります。例えば、よく使う言葉の
外国人に初めて日本語を教える際、「標準語は~だけど、大阪弁は~のように言うから両方覚えて下さい」というようには教えないでしょう。日本手話も同様で、同じ単語を表すにも「~という表現もあるし、~という表現もある。~というように表現する人もいる」と言う教え方では、初心者が覚えるのは非常に大変です。すべてがごちゃごちゃになって、手話を習得する意欲が減退してしまう人も出てくると思います。
今は、インターネットで日本中、さらに世界中がつながっている時代です。そして、言語とは、やはりコミュニケーションの道具としての役割が大きいと思います。手話を学ぶ聴者だけでなく聾者自身も、多くの人に通じる「標準手話」を意識することが必要なのではないかと思いました。明治から大正にかけて、日本語の標準語が普及していったことと同様にです。そうすることで、手話がもっと普及し、聴覚障碍者に対する聴者の理解も深まるのではないかと考えます。
手話奉仕員養成講座と手話通訳者養成講座
…手話を使えるようになることと、手話通訳になることは、全く別なのに…?
*手話奉仕員養成講座を終えて、個人的に思ったこと
《最終更新日: 2024年6月16日》
私は、2022年5月、「聾者の知り合いとスムーズにコミュニケーションを取れるようになりたい」という理由で、居住地の市の広報で見つけた「手話奉仕員養成講座」を受講することにしました。ある日、実務講座の途中に受けた「講義」の時間、講師の先生からいきなり、「手話通訳の服装は黒か、最低でも無地が基本なのに、柄物やボーダーのTシャツで来るとは受講生としてなっていない」と言われました。あらかじめ服装の指定があったわけではなかったので、不快な気分にもなりました。また、講習会の感想や質問を、パソコンのワープロソフトで仕上げて提出していたところ、「通訳になるためには手書きの技術が必要なので、パソコンは使わないように」と言われ、正直かなり戸惑いました。
私は、実際、手話通訳になりたくて手話奉仕員養成講座に応募をしたわけではありません。モヤモヤした気持を解消するために、ネットで主催者について調べてみて、初めて、この講座が「手話通訳養成講座の前段階に位置づけられている」という事がわかりました。それならば講師の先生の言動も納得いきますが、最初に周知されなかったことに問題を感じました。
「手話を話せるようになること」と、「手話通訳をできるようになること」は、全く別次元の話と思います。英語の通訳をするためには、ただ英語を話せるのとは全く違う、技術やレベルの高さが求められるので、それと同じと思いました。
結局、講座について問題と感じたのは、講座の主催者側と受講者側の意識のズレです。もちろん「手話通訳」を目標に頑張っている方もいらっしゃいます。ただ、途中で受講を断念された方の中には、「手話通訳を目指す講座のレベル」と「手話を使えるようになりたい受講者の考えるレベル」のズレを感じた方もいると思います。講座自体は、講師の先生方のパーソナリティーも内容も素晴らしく、とても意義深いものだったので、とても残念です。
手話通訳者を養成することは、もちろん必要なことと思います。しかし、もっと気軽に手話を学べる環境を整え、手話に理解のある人のすそ野を広げていくことも、重要なのではないかと思いました。中途聴覚障碍者や難聴者も気軽に学べるわかりやすい手話。そんな手話が普及し、障害のあるなしに関わらず、皆が楽しくコミュニケーションを取れるようになればと思います。
状況別に必要な手話の能力
聴者に必要な手話の能力は、状況によって違ってくると思います。自分が英語が下手な頃から、外国人と交流した経験から考える、必要な能力について書き留めてみました。自分がどんな状況で手話を必要としているか、そのために必要な能力が何か、考える参考にしていただければと思います
①聴者が大勢いる中で、聾者が1人の場合
*聴者の話している内容を、聾者に教えてあげたい。
*聾者と親しくなりたいから、自分を知って欲しい。
…ここで一番必要なのは、手話が下手でも良いから伝える能力です。ジェスチャーや表情の変化も多いに活用して、とにかくコミュニケーションを取ろうとする気持が大切です。きっと喜んでもらえると思います。
②聾者が大勢いる中で、聴者の自分が1人の場合
*聾者同士だから手話のスピードはものすごく早い。これは英語ネイティブが多い中に、ネイティブでない自分が1人居る場合と同じです。
…ここで一番必要なのは、色々な手話を読み取る能力です。この力をつけるのに必要なのは、学習者のレベルに合った教材で学ぶことです。いきなりナチュラルな英語が使われる映画を見ても、理解するのが困難なように、聾者同士のナチュラルな手話を理解するのは、初心者にはむずかしくて当然です。可能ならば、1対1でゆっくり手話を使ってもらいましょう。
③手話通訳の場合
*色々な地域や、年代で違う手話を正しく読み取り、適切な日本語に瞬時に訳したり、逆に色々な日本語を簡潔な手話に直す必要がある。
*自分が興味のない話題、専門外の話、最新の情報なども訳さなければならない。
…ここで求められるのは総合的な手話の能力と国語力です。
英語の通訳と似ていると思います。英語でも一般的に個人で学習するのはアメリカ英語かイギリス英語の一種類です。そこそこ習得できれば、十分コミュニケーションを取れると思います。しかし通訳では、地域や世代で変わる英語も理解する必要があります。さらに、話し手の伝えたいことを瞬時に理解し、簡潔な日本語に直す国語力も何より重要となります。手話通訳も全く同様かと思います。
…さらに、自分がよく知らないことを通訳するのは困難です。常に色々ことに興味を持ち、幅広い教養を身につけることも求められると思います。
長く英語学習に関わってきた者として、日本手話を学んで気づいたことがあります。それは、英語との共通点がとても多いということです。英語を学ぶ前に、手話に少しでも触れておくと、英会話などにも役立つテクニックが詰まっています。
詳しい説明は、別ページにまとめましたので、
さらに、共通点をまとめていく中で気づいたことがあります。それは、手話はコミュニケーションを取るのにとても優れた言語ということです。英語は色々な国の人が使う言語ですが、手話の基本が分かっていると、耳の聞こえない人どうし、使う言語が違っても、ある程度のコミュニケーションが取れるようです。
難聴や中途失聴者で手話がわからない人も多いと聞きますが、コミュニケーションを取るのに優れた言語である手話を、是非習得して欲しいと思います。きっと世界が広がると思います。そのためにも、意欲のある人達が簡単に手話を学べることができる環境が整うことを期待します。
1.表情が大事
2.表現の強弱とイントネーションが大事
3.主語の明確化が大事
4.意味をつかんだ具体的な表現が必要
*オノマトペ(擬音語や擬態語)はあまり使わない
5.1つの単語で色々な意味を持つ言葉が多い
6.文章を作るコツは簡潔でわかりやすい表現を‼
*接続詞の使用頻度が日本語ほど多くない
7.1度覚えたら終わりではなく継続が大事
手話言語条例について
手話言語条例を作る必要性は何か?
私が居住する町でも、現在、手話言語条例を作る話が出ています。ただ、条例が成立することで、何か良いことがあるのか、私自身よくわかりません。
昔は、手話が認められず、手話を使いたい聾者が大変な苦労を強いられたことがあると学びました。ただ、現代は、多様性を重んじる時代です。公共放送のNHKなどでも、手話がかなり取り入れられています。ドラマなどで取り上げられる機会も増えています。「手話が聾者の言語」ということは、すでに多くの人が認知しているのではないかと思います。
そんな中、手話言語条例を作る必要性について、私なりに考えをまとめていきたいと思います。何か、ご意見などありましたら、HOME内のメールからご連絡頂けると幸いです。《2024年8月18日現在》
*聾者の気持は?
手話言語条例を作るにあたり、一番大切なので、それを使う聾者の皆さんの気持ではないかと思うのですが、そもそも聾者の皆さんは、この条例に何を期待されているのか、必要性を感じていられるのか、実はよくわかりません。何故なら、それについて、じっくり話し合ったことがないからです。
もし、話し合いが行われ、聾者の気持、希望などをお聞きできたら、こちらのページにアップしていきたいと思います。
*聴者の立場で思う、日本手話の魅力:
個人的には、「日本手話はとても役立つ言語」であると、手話を学んでいて思いました。なぜなら、日本手話は、多くの内容を簡潔に、論理的に伝えられるように工夫されていてることが分かったからです。
英語教育に関わってきた者としては、日本手話を学ぶと、英会話を学ぶ時にも大いに役立つと感じています。(参考:
また、指を使う手話は、認知症の予防にも役立つとの話も聞きました。超高齢化社会に突しつつある中、多くの人が手話を学べる環境を整える事も意義深いと思います。
日本手話の優れた点を感じてきました。それを多くの人に伝えられないかと思います。学校の義務教育の一貫で、手話や聴覚障害者について学ぶ時間を作って頂けないかと思います。(一部の学校で、不定期に手話体験学習というものは行われているようですが、そういうことではなく、市内の全学校で、年に1回は必ずやるなどです。)
因みに、難聴の人で手話を学ばない人も多いと聞きますが、残念です。難聴の人や中途失聴者にも、手話はとても役立つ言語であると思います。
先日(2024年6月)、デフリンピックのバレーボール日本代表選手の話をZoomで聞く機会がありましたが、チーム内のコミュニケーションは手話を使うとのことでした。難聴の選手は口話が中心の生活だったようですが、手話を覚えてろう者ともコミュニケーションを取っているとのことでした。
*聾者への理解を深める必要性
身体障碍者や盲者ならば、見てすぐ「障害がある」と気付けますが、聾者の障害は、他者からわかりずらいです。そこに多くの問題があると思います。
「ろう者は自分の声や自分の行動で起きる音が聞こえないので、驚きで発する声が大きすぎたり、ステーキの肉を切る時、スープをスプーンで飲む時、不快な音を出してもわからない。それを理解して欲しい。変な目で見られるのがつらい。」
この話を初めて聾者に聞いた時は驚きました。知らなければ、他者の立場に立って共感することもむずかしい思いました。
また、聾唖者と聾者の違いがわからない人は多いのではないでしょうか、
ろう者は耳が聞こえないだけで、声を出せる人も多いです。中途失聴の人や、聴者にもわかる言葉を話す適性があり、訓練したろう者の中には、、相手に通じる言葉を話せる人もいます。(口話法)ただ、誰でもできるわけではありません。
また相手の唇の動きを見て言葉を理解できる(口話法、読唇術)人もいますが、これも皆ができるわけではありません。昔の教育では口話法重視の時代もあり、今も「口話法が普通」と思っている人もいると聞きます。もっと、聾者のことを知ってもらう必要があると思います。
手話のサークルに入るとか、支援団体に入るとかではなく、もっと気軽に、聾者と聴者が交流できるような機会があればと思うのです。
↑聴者にはわかりにくい事なので、お読みいただけたら幸いです。
*ろう者や難聴者に対する教育の重要性
聾者と盲者を比べた場合、障害の程度は盲者の方が苦労が多いと思われます。しかし昔から、例えば江戸時代に、盲者は按摩やごぜ(盲女・三味線を弾き唄を歌って銭を稼いだ)などの仕事がありましたが、聾者は大変だったようです。聾学校があったわけではないので、環境によっては、聾者は聴者とコミュニケーションをとる手段がなく、教育も受けられず、言葉も理解できなかったそうです。手話で正当な教育を受けられれば、才能や能力を開花させられる機会も得られたはずなのに、その機会がなく、「無能、馬鹿」と罵られる不当な扱いを受けた人も多かったと聞きます。胸の苦しくなる話です。
聾学校で、手話を含めてしっかり教育を受けた聾者は、知識が豊富で、活動的な人が多い印象です。逆に、普通学級に通う難聴者が、先生の声が聞こえづらく、授業についていけなくなったという話も聞きます。教育格差が広がらないような配慮も必要と感じます。
*家庭での問題
一言でろう者と言っても、家族全員が聾者のデフファミリー、親が聴者で自分だけが聾、兄弟は聴者で自分だけ聾など色々あります。
デフファミリーで、幼少期から手話を使い、聾学校にいける人は、カナダの聾学校の寄宿舎で生活する生徒と同じにように、自己肯定感が強く、明るく活動的な人が多い印象を受けます。(参考
難聴者や中途失聴者の場合、手話もできず、学校でも、授業での先生の話が良く聞こえず、成績が悪くなり、自信を失ってしまう人もいるとのことです。
「保護者が、難聴の子供に普通学級での教育を選択することで、子供に不利益が生じていないか。」「公共機関が何らかの助言やサポートをできないか。」考える必要があると思います。
手話が「特別なもの」ではなく、「言語」と認識されることで、差別的な考えが軽減されることを願います。
*手話の習得を困難にしている原因は何か?
①自習できる手段の不足:
「手話はコミュニケーションの手段ではなく文化」と教える聾者をサポートしてきた大学教授の話を聞きました。「手話は、聴者ではなく、聾者の物なので、実際に聾者から学ぶべき」という話も、何度も聞きました。
しかし、手話を「言語」とするならば、外国語と同じように、聾者、聴者関係なく、誰でも気軽に学べるものにしていく必要があると、私は考えます。
「手話をしっかり見ていれば読み取れる。手話を学ぶには、ろう者と交流すべき。」と色々な機会に言われましたが、見ただけで手の動きを把握する理解力には、個人差があると思います。また、言語というのは、くり返し使わないと習得できないので、普段、聾者と交流する機会のない人ならば、自習をできる手段が必要です。手話の講習会や手話サークルに参加しただけでは、なかなか会話できるレベルにはならなくて当然です。
②「標準手話」の不確立:
手話は地域ごとに方言が多く、基本的な単語でも、色々な表現がある場合も多いです。ただ、通訳になるならともかく、日常会話をできるレベルになりたいならば、とりあえず手話の共通語と言える「標準手話」を1つだけ覚えたいところです。しかし、それが何かわからない。手話言語研究所で標準手話や新しい手話を考え、動画なども公開していますが、手話を教える立場にあるような人も、その手話を知らないことにも多くの問題を感じます。(参考
「日本手話は文法なども含め日本語と全く違う。」「日本語対応手話は日本手話ではない。」との説も聞きますが、ちゃんとした教育方法があれば、日本人が英語を学ぶより、日本手話を学ぶ方が遙かに簡単です。標準語としての日本語は、明治維新後に多くの困難を乗り越えて確立されたと聞きます。そのことが日本人の相互理解を深めたことは間違いないと思います。「日本手話」も、そうなって言って欲しいと思います。
*聾者が聴者とコミュニケーションを取りたい時、工夫も必要?
聴者として、聾者とコミュニケーションの取る時に特に困ったことは、「話のテーマが急に変わると、話についていなくなる」という事です。
また、話の途中で、「聞き手の知らない人の名前を急に出す」時も、伝わりにくいです。
自分で手話で話をどんどん進めてしまうと、手話通訳がいる場合でも、通訳がしっかり日本語に直せず、聞き手に伝わらない自体も生じます。
コミュニケーションは、自分が伝えたいことが、しっかり相手に伝わることが大切です。話が長くなる時など、途中で自分が伝えたいことが相手に伝わているか、確認すると良いのではないかと思います。
英語でコミュニケーションを取る時も感じますが、わからない時にわからないと言えない日本人が多いと思います。自分では話が伝わっていると思っても、実は伝わっていないこともあると思います。そのことを踏まえて、コミュニケーションを取る工夫が大切と思います。
自分が伝えたいことを伝える権利が、聾者にはあります。伝わらないことを諦めて欲しくないと思います。
*以下、市の手話サークルの広報に掲載された私の書いた文章抜粋:
「手話言語条例の制定についての勉強会」に参加して
2024年9月15日(日)、手話言語条例の制定についての勉強会に参加しました。講師は、全国手話通訳問題研究会の先生。出席者は市内29人、市外23人の計52人(内、聾者11人、難聴者3人)で、要約筆記サークルにもご協力いただきました。
今回は講義だけではなく、7グループに分かれてのグループ討議もあり、色々な意見を聞くことができました。特に、すでに言語条例が制定されている市の参加者から、「条例ができたことで、意見交換会ができ、当事者の権利が主張できるようになった。ただ条例は、できて終わりではなく、その意見を反映しながら変えていく必要がある。」というお話が印象的でした。
「聞こえない人は手話による情報が入ってこないために、自分が不利益を受けていることに気づかないこともある。医療機関や行政手続きの際に、自分の言葉である手話を選択できるようにするにはどうしたら良いか。」複数の手話通訳者の市正規職員への採用、学校教育での聴覚障害者や手話への理解の浸透など、今回の勉強会を通して、聴者としても、今後考えていくべき課題が見えてきた気がしました。
個人的には、SDGs(持続可能な開発目標)の中の「誰一人取り残さない」というスローガンを思う時、このような勉強会に、市の職員、教育関係者、条例制定に関与する市議会議員の方々にも、参加していただきたいと思いました。
地域の手話出前授業の様子
2024.08,29
地域の小学校の放課後クラブ(学童保育)での出前授業に参加しました。
手話の歌「さんぽ」の歌詞の説明をしていた時、「『あるこう、あるこう』の手話は、人差し指と中指で脚の動きを表しているんだよ」と言うと、「首がないじゃん」と男の子の声。よく観察しています。
その時は時間が無く、答えられなかったのですが、この観察眼を褒めた上で、「手話は見て、すぐ理解できる言語として、いかに素晴らしいか」を説明できれば、よりよい授業になったかと思いました。
例えば、ヨロヨロして酔っ払いの千鳥足を表せる。さらに転んで見せたら、インパクトがあったかもしれません。エレベーター、エスカレーターなどもすぐわかる手話なので、「クイズ形式」にするのも良いかと、アイデアが湧きました。
以前、青少年相談員をしていた時、250人ほど集まる大会で、手話の挨拶を、クイズにすると、会場の多くの子供が大きな声で答えて、これも、ただ説明するのと違って、インパクトがあるかな~と思いました。
「挨拶」を教えた後、「起きる+挨拶=おはよう、昼+挨拶は何?」など。「暗くなる+ご飯=夜ごはん」などもいけそうです。
子供の人数が多いと、聾者とコミュニケーションを取る時間が限られてしまいます。それを踏まえると、皆で盛り上がれそうな工夫もあると良いかと思いました。
授業を進める際に、サポーターが多ければ、子供達の間に入ったり、脇や後ろについて、「できたかな~。上手だね~。(次の話題に進むから)前に集中!」など、そっと声をかけてあげると、さらに子供達も意欲が湧くと思いました。指を器用に動かすのが、なかなかむずかしい子供もいますから…
プログラムの途中、私が子供達の後ろに控えていると、「源氏物語の手話はどうやるの?」と真剣に聞いてきた子供が居ました。「手を上げて質問してみたら」と促したのですが、結局機会がなく、「最後に必ず教えてあげる」とその場は約束しておさめました。サークルの先輩にやり方を聞き、全部のプログラムが終わった後にこそっり教えてあげると、とても喜んで、何度もその手話を練習していました。すると他の子供達も集まってきて、「僕の名前、どうやるの?」「ブドウはどうやるの?」「また来てくれるの?」と、次々と尋ねられました。皆の前に出て聞くのは勇気がなかったか、手を上げても指されなかったのか。子供達は手話歌を歌って、テンションが上がっていたのかもしれませんが、久しぶりに子供達にぎゅっと抱きつかれ、少しでもこんな時間があると、サークルの皆さんも子供達も、より楽しいのかな~と思いました。
最後に余談ですが、以前、私がニュージーランドからの留学生を連れて小学校に行った時、子供達が話したい英語を私が教え、それを実際に留学生に通じるかやってみるという機会がありました。留学生と英語でコミュニケーションを取れた時、留学生も子供達も幸せそうでした。
手話も同じなのかと思いました。今回、聾者は3人参加してくれ、さらにサポーターもたくさんいたので、3グループに分けて、1人1文づつでも、聾者と手話を使ってコミュニケーションをとれるようにしたら、「手話は聾者の言葉」とより感じられたのかと思いました。
「手話を教えるのが聾者というのではなく、手話でコミュニケーションを取れる相手が聾者」という視点もありなのかと思います。「源氏物語」の手話を聞いてきた子は、本当は、「私は源氏物語が好きです。」という事を、手話で聾者に伝えたかったのかなと思いました。
最後に…
2年間、「聴覚障害者支援員養成講座」で勉強してきて、手話表現の豊かさ、聾者とコミュニケーションを取れる楽しさを学ぶと同時に、聾者が日常生活で困ることや、聾教育の歴史から見える聾者の被ってきた数々のご苦労などを知ることができました。
現在、ようやく日本手話が言語として法律的にも認められるようになったと伺い、大変嬉しく思います。ただ、高齢の聾者の中には、十分な手話教育を受けられず、一般的な手話がわからない人もいたり、中途失聴や難聴の方だと、やはり手話を習っていない人も多いということもわかってきました。
こちらのページを作成するにあたり気付いたのは、日本手話を独学で習得することがとてもむずかしいという事です。手話には方言も多く、簡単な単語の手話表現を、本やネットなどを駆使して調べようとしても、なかなか簡単には見つけられず苦労しました。このような状況では、手話を学ぶのは、英語を学ぶよりもむずかしい気もします。(2024年3月に改訂された![]() NHK手話CGで、かなり良くなりましたが…)
NHK手話CGで、かなり良くなりましたが…)
講座を終了する前は、聴者や中途失聴者は、まず日本語対応手話を習得できるようにし方が良いとも思っていました。しかし、![]() 手話を覚える時、知っておきたいポイントでも書いたような、簡単な手話の文法(手話の法則?)さえ押さえておくと、日本手話は見てすぐ理解でき、聾者が効率的にコミュニケーションを取れるように工夫された、とても優れた言語であるとわかりました。より多くの人に知って欲しいところです。
手話を覚える時、知っておきたいポイントでも書いたような、簡単な手話の文法(手話の法則?)さえ押さえておくと、日本手話は見てすぐ理解でき、聾者が効率的にコミュニケーションを取れるように工夫された、とても優れた言語であるとわかりました。より多くの人に知って欲しいところです。
そんな手話ですが、私が学習者として一番問題であると感じることは、簡単な単語を表すにも、標準手話が確立されていないという事です。(火曜日、1時間など色々)
これは、手話の学習を始めてから今まで、ずっと感じ、モヤモヤしていることです。誰かが、「日本手話はむずかしい言語」と思わせるため、わざわざ高い壁を作っているような気さえします。
日本語の標準語も、明治維新後、全国の交通網が整備され、人の往来が盛んになる中、必要に迫られて標準語を作ることになり、大正時代になってようやく定着してきたと聞いています。インターネットが普及し、世界とも簡単に繋がりを持てるようになった現在、皆が理解でき、皆が簡単に覚えることができるように、標準手話を整えていくことが必要なのではないでしょうか。それが日本手話の普及、聾者への理解、さらに聾者と聴者の壁をなくすことにつながっていくのではないかと思うのですが…。
| 年代 | 国内 | 海外 | その他 |
| 1878年 M11 |
京都盲唖院(現京都府立聾学校)設立/ (日本初のろう学校。当初は聴覚障害、視覚障害の統合校) |
||
| 1880年 M13 |
イタリア・ミラノ 国際会議 手話法より口話法の方が優れていると宣言 |
||
| 1920年 T9 |
…口話法の教育開始 |
||
| 1923年 T12 |
盲学校及び聾〔唖〕学校令の制定 …盲聾分離 (1899年に小西信八、1906年に古河太四郎などによって陳情されていた) |
||
| 1947年 S47 |
群馬県伊香保温泉にて創立 |
||
| 1948年 S23 |
第1回全国ろうあ者大会開催 (京都) |
||
| 1950年 S25 |
「財団法人全日本聾唖連盟」設立認可(厚生大臣) | ||
| 1963年 S38 |
手話学習会「みみずく」創立(京都)…後に全国的に結成されることになる手話サークルの初まり | ||
| 1966年 S41 |
第1回全国ろうあ青年研究討論会の開催(京都) | ||
| 1967年 S42 |
第1回全国ろうあ者体育大会の開催 (東京) |
第5回世界ろう者会議(ポーランド)に初の日本代表団派遣 | みみずく会手話通訳団発足 代表:向野嘉一(こうのかいち・京都) |
| 1968年 S43 |
第1回全国ろうあ者冬季体育大会の開催(群馬) | *第1回全国手話通訳者会議(福島市民センター)「手話通訳者の語り合う場が必要/京都がやらないことをやろう/71人(26人) | |
| 1969年 S44 |
「わたしたちの手話」 /全日本ろうあ連盟が発行 …手話をイラストで紹介した日本初の本格的な手話単語集。これが「標準手話」として位置づけられる。 |
||
| 1970年 S45 |
* 「手話奉仕員養成事業」開始…ろう者に理解のある家庭の主婦など | ||
| 1972 S47 |
*第5回全国通訳者会議(長野/250人) 会長は |
||
| 1973年 S48 |
*「手話通訳設置事業」開始 | 自動車運転免許取得を補聴器着用条件で可能に/警察庁が通達 | |
| 1974年 S22 |
全日本ろうあ連盟設立 (会員資格をろう者とする団体) |
*第7回全国通訳者会議(青森) 全通研「全国手話通訳問題研究会」を個人加盟の全国組織として結成/会員287名/初代運営委員長=伊東 雋祐 |
|
| 1976年 S51 |
全日本ろうあ連盟による手話通訳認定試験の開始 | *「手話奉仕員派遣事業」開始 | |
| 1979年 S54 |
厚生省委託の「手話通訳指導者養成研修事業、標準手話研究事業」の開始 | 第8回世界ろうあ者会議 | |
| 1985年 S60 |
「手話通訳制度に関する検討報告書」を厚生省へ提出/ 「アイ・ラブ・パンフ」120万部普及運動開始 |
||
| 1986年 S61 |
ろうあ立候補者の政見放送に手話通訳認めず 政見放送について全国的運動の展開 |
||
| 1989年 H1 |
*手話通訳士認定試験(厚生大臣) 筆記試験:1097人(合格者609人) |
||
| 1991年 S3 |
第11回世界ろう者会議開催 (日本での初開催・東京) |
||
| 2001年 H13 |
法律での欠条項廃止へ/道交法・医師法 ろう者に初めて薬剤師免許交付 |
||
| 2002年 H14 |
「社会福祉法人全国手話研修センター」発足 | ||
| 2006年 H18 |
「手話は言語である」と定義した「障害者権利条約」が国連総会で採択 | ||
| 2007年 H19 |
特別支援教育制度始まる/聾学校は「特別支援学校」に…他障害児学校との統合・併設には反対運動が展開 | ||
| 2008年 H20 |
道交法改正/ワイドミラーと聴覚障害者マークの装着を条件に全く聞こえないろう者の運転免許取得が可能に | ||
| 2011年 H23 |
「障害者基本法」の改正 …手話が言語として位置づけられる |
「We loveパンフ」21万部超普及/116万筆超えの署名を集めて政府に提出 | |
《オープンスクール感想等》
全通研の歴史や初期の頃の手話通訳をされていた方のご苦労、頸肩腕障害などのこともわかり、大変勉強になりました。
当日質問できなかったのですが、「全日本ろうあ連盟による手話通訳認定試験の開始は1976年」、参考資料にあった「手話通訳士認定試験の開始は1989年?」この辺りの関係がよくわかりませんでした。
2002年に発足した「社会福祉法人全国手話研修センター」 で標準手話などが載っているサイトがあるのですが、こちらと全通研とは協力関係にあるのでしょうか。
ろう者や手話との関係が浅い一般人には、各組織の名前が似ていて、違いがよくわからないので、そのあたりについても今後お伺いできれば幸いです。
(1845-1907)
京都盲唖院(後の京都府立盲学校・京都府立聾学校)を創設し、近代日本での視覚障害教育・聴覚障害教育の黎明期をリードした。
彼の没後30年に当たる1937年にはヘレン・ケラーが、彼の創設した聾唖学校を訪問している。
He founded the Kyoto Institute for the Blind and Mute (later the Kyoto Prefectural School for the Blind and the Kyoto Prefectural School for the Deaf) and led the early days of blind and deaf education in modern Japan.
In 1937, 30 years after his death, Helen Keller visited the deaf-mute school he founded.
1875年、彼が寺子屋の教師だった時代に、聾唖の生徒が日常的に使用していた手話に着目し、体系的な機能を持つ言語としての教授用の手話を考察した。
この際に考案された表現方法をが、現在、標準手話として制定されている日本手話の原型となっている。
In 1875, when he was a terakoya teacher, he focused on the sign language that deaf-blind students used on a daily basis and considered sign language for teaching as a language with a systematic function.
The method of expression devised at that time became the prototype of Japanese sign language, which is now established as standard sign language.
1879-1971
駐日アメリカ合衆国大使を務めた
1905年に妻ヘレンとともに宣教師として来日。1914年に再来日し長女フェリシアが生まれる。長女は熱病のため幼くして聴力を失う。当時の官立東京聾唖学校の小西信八校長は、米国に帰って口話法による教育を受けるように助言し、さらに日本にも口話法の聾学校を作って欲しいと依頼した。
名古屋市聾学校の校長を務めた橋村徳一の口話教育への推移
1912-13 (T1-2) 手話期
1914 (T3) 混合期
1920-28 (T9-S3) 口話期
参考:
松永端の「手話辞典」
(?1990-?)
…大阪市ろう学校の教諭であった松永端(まつながたん)が編集、発行。
指文字以外はイラストはなく、文字でてなどの動きを説明。
地名、数詞、指文字などを含めて見出し語数は2,137単位。
(内、手話単語の数は1,000単位程度)
金田富美「手話」
…国立ろうあ者更生指導所言語課職員であった金田富美が、早稲田大学ろう心理研究会などの協力を得て、編集、発行。
日本初の写真による手話単語集。
掲載手話単語は765語とこれ以外に指文字(イラスト)を掲載。
金田富美は1980年(S55)にも、本人の写真で手話を表した「日本手話辞典」を発行。
ただし、これ以降の手話自演は、イラストの手話が主流となります。
